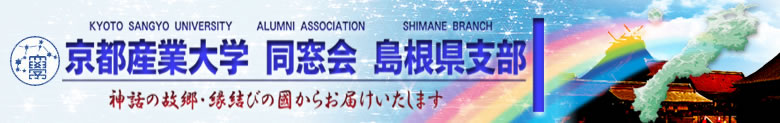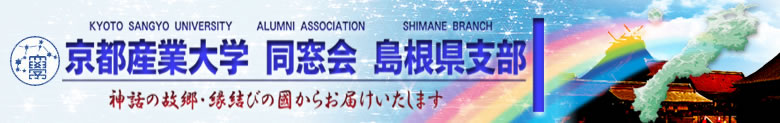私は2006年の 7月、結婚を機に大学時代を含め8年間過ごした京都から10年ぶりに帰郷いたしました。故郷を離れていた10年間は大きく、大学時代を懐かしく思い浮かべながら今、この地に慣れる努力をしているところです。
今年 1月には、長男 建(たける)が誕生し、子どもの可愛さに無上の喜びを感じながらも親として責任をひしひしと感じるこの頃です。
去年の 10月京産大島根支部総会において坂井学長の講演をお聞きする機会に恵まれました。大きな夢をもって帰郷したものの希望と不安の行きかう毎日を送っていた私に、坂井学長は「人生、何事も挑戦しなければ、成功も失敗もない。失敗をおそれて何もしないというのが、人間そもそもの失敗である」と大きな勇気と力をくださいました。
そして長年温めてきた「居酒屋」オープンの夢に向かって、失敗を恐れず、京産魂を胸に何事にも果敢に挑戦していきたいと心を強くいたしました。
現在、夢を実現すべく日々努力を積み重ねている所ですので、同窓生の皆様のご指導、ご支援を宜しくお願いいたします。オープンの折りにはぜひ、ご利用くださいますようお願いいたします。
京都産業大学理学部数学科を平成17年に卒業後、京都市内にある私立高校で数学非常勤講師として半年間勤務した後に、青年海外協力隊理数科教師として西アフリカのガーナ共和国に赴任しました。
初めの1年間はセントラル州にあるアゴナスウェドル教育事務所にて、現地の中学校数学教師の能力向上を目的として授業を見学してその授業に対してアドバイスをすることが私の仕事でした。初めは外国か
ら来たお客さんのような扱いを受けていたので、上手く仕事相手としてコミュニケーションがとれていませんでした。良い関係を築いていくために無理に仕事の話をせずに相手の話を聞いたり、厳しいことを言わずになるべく相手のことを褒めるようにしました。仕事を始めて3か月くらいが経過してからは、外国人という壁が少しずつ取れていきました。近所や町にも友達ができて、プライベートでも楽しんでいけるようになりました。上は現地の先生が数学の授業を行っているところです。
左:ガーナ人はいつも頭の上に荷物をのせて運びます。
上:運が良ければカメレオンが見られます。
ガーナで一番良いと思ったのはやっぱり子供。人懐っこさは誰でも嬉しく感じるはず。子供たちに何度も元気づけてもらいました。ガーナの子供は小さい時から家のお手伝いをよくします。5人以上の兄弟がいることがほとんどなので、子供が料理、洗濯、掃除をして両親は寝ているという光景をよく目にしました。ガーナの子供は働き者でとても感心しました。ガーナに来て1年後にジャシカン教員養成校に赴任しました。日本にある教育大学と同じで将来の先生を育てる大学で、数学とコンピュータの授業を担当しました。1日平均5時間の授業があり、大変でしたが、全寮制の学校だったので生徒と同じ給食を食べることができたので、生活は前より楽になりました。
左の写真は、2年生が模擬授業を行っているところです。この学校では3年生になると1年間の教育実習に行きます。そのため2年生から教育実習に行くために授業の練習をします。他の生徒は小中学生の役をしています。私も席に座って授業を見学して、終了後にアドバイスします。中には間違ったことを教えていることもあるので、集中して聞かなければなりません。しかし生徒は一生懸命なので、その必死さが見ていて楽しかったです。
右の写真が3年生の教育実習の様子です。生徒は中学2年生で、青いシャツを着ているのが私の生徒です。教育実習といっても日本とは違って、先生の業務をすべて行います。中には教育実習生にほとんどの授業をやらせていて、本当の先生は休憩中なんてことも…。そのため実習生は毎日が大変で、ヘトヘトになっています。
次の写真はコンピュータの授業風景です。十数台のパソコンがありますが、ほとんどが故障していたために始めは修理ばかりしていました。なんとか直せたのは5台でした。ほとんどの生徒がパソコンを触ったこともないため、マウスの持ち方や電源の入れ方などの指導から始めます。もちろんインターネットには接続していません。E-mailを送りたいときは車で3時間の町に行けば送ることができます。 ガーナの学校でも日本と同じように長期休みがあります。その間は仕事が少ないために、他の日本人ボランティアと一緒に様々なイベントを企画しました。
2枚の写真は80人の生徒を招待して実験授業中心のサマースクールの様子です。左は粉じん爆発の実験、上はペットボトル噴水作りの写真です。いろいろな地域から生徒が集まって5日間様々な授業を受けました。ガーナでは備品不足や知識不足から理数科の授業で実験を行う機会がとても少ないため、生徒たちは始めて見るものばかりでとても興味津々でした。
左の写真は、パソコンの設備が整っていない学校で、パソコンを使用したことのない生徒を対象とした出張型コンピュータ教室の様子です。1週間で3,4校を訪問して2時間の授業を午前と午後の2回行います。ワードを使って自分の名前を入力してデジカメで撮影した写真を添付、そして印刷をします。自分の写真を印刷したら生徒はもう興奮状態です。
ガーナにおいて経験したことは、日本では得られないものばかりでした。水が出ない、停電が毎日、モノがない、無い無い無い!!ばかりの生活でしたが、人の優しさ、生き抜く力は素晴らしいと感じるばかりでした。毎日笑顔と元気を届けてくれた、生徒たち、同僚、近所のおばちゃん、子供たちに感謝いっぱいです。